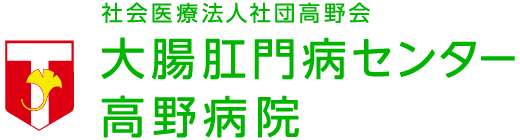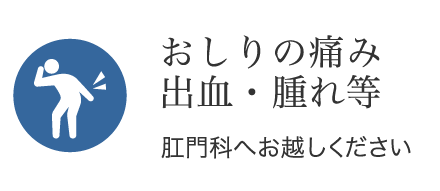疾患情報
消化器外科
鼡径(そけい)ヘルニア
鼡径(そけい)ヘルニア
| 鼡径(そけい)ヘルニアとは 足の付け根部分のことを「鼡径部(そけいぶ)」といいます。 「ヘルニア」とはもともとはラテン語で飛び出すという意味で、 鼡径ヘルニアとは足の付け根から小腸やお腹の中の脂肪などの組織が出てくる病気です。 本来ならばお腹の中に収まっているはずの腹膜や腸の一部が、鼡径部の筋膜の間からはみ出して皮膚の下に出てきてしまう、俗にいうところの「脱腸(だっちょう)」のことです。 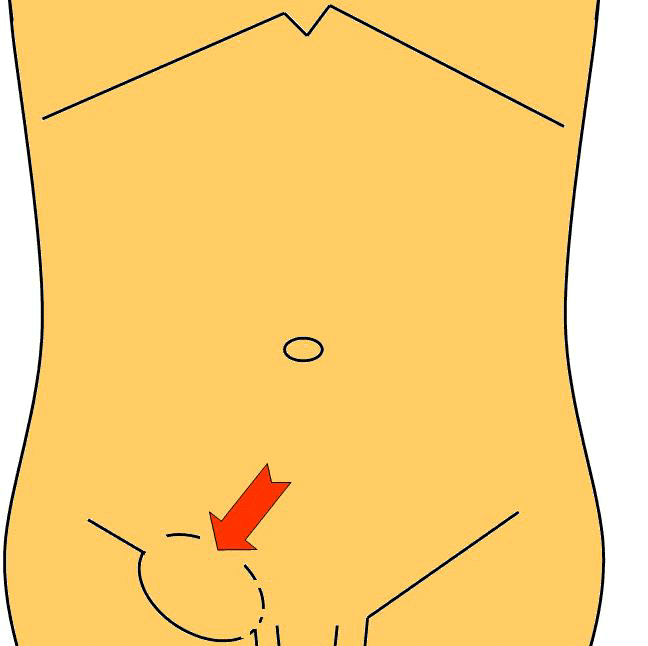 鼡径ヘルニアの【原 因】 鼡径ヘルニアは、子供では先天的なものが多く、大人では加齢によって筋膜が弱くなることが原因と言われています。 40歳以上、特に60歳前後の男性に多くみられ、ときに陰嚢(いんのう)まで脱出が及ぶこともあります。 女性の場合は男性に比べ少ないですが、20~40歳の鼡径ヘルニアが多い傾向があります。 鼡径部は筋肉や筋膜が複雑に重なり合った構造になっています。
鼡径ヘルニアの【症 状】 重いものを持ち上げたり、咳き込んだりしたとき、力んだときなどお腹に力がかかったときに足の付け根近くにふくらみを触れたり、突っ張り感、違和感などを認めます。ヘルニアの程度が軽いうちは、ふくらみは寝たり、押さえると引っ込んで戻ってしまい、特に痛みも無いことが多いです。 ヘルニアの程度がすすんでくると、違和感が強くなったり、ふくらみが大きく・硬くなったりします。押さえても戻りにくくなり、痛みや吐き気を伴うこともあります。 脱出した腸が戻らなくなり、根本で締め付けられると(かんとんといいます)腸の血行障害を伴い腸管の穿孔(せんこう)など重篤な合併症を起こすこともあります。このような場合、早急に治療を受ける必要があります。大腿ヘルニアでは腸が出てくる穴がせまく、かんとんを起こしやすいといわれます。
鼡径ヘルニアの【検 査】
鼡径ヘルニアの【治 療】
鼡径ヘルニアの【手 術】 鼡径ヘルニアの手術では、でっぱっている袋状の腹膜(ヘルニア嚢)を切除し、ゆるんだ筋膜や筋肉を補強することが基本となります。補強方法として前方から行う鼡径部切開法(メッシュプラグ法やリヒテンシュタイン法)と、後方(腹膜側)から行う方法(クーゲル法や腹腔鏡下ヘルニア修復手術)があります。当院では主にメッシュプラグ法やリヒテンシュタイン法と腹腔鏡下ヘルニア修復手術を行っています。
[鼡径部切開法] いろいろな術式がありますが、高野病院ではメッシュプラグ法及びリヒテンシュタイン法を基本としています。 20年以上前に行われていたメッシュを使用しないヘルニアの手術(従来法)は、ヘルニア嚢を切除し、ゆるんで腸がでてくる部分を縫い縮めてでにくくするとともに、筋肉や筋膜を縫い寄せて補強を行う方法でした。しかし、この筋肉や筋膜を縫い寄せる際、非常に緊張がかかるため、術後のつっぱり感や痛みが長く続く欠点がありました。再発率も2~10%と報告されています。 合併症として気をつけなければいけないのが感染症です。通常無菌手術でおこなわれますので感染はごく稀ですが、創部に感染がおき、メッシュに及んだ場合人工物は感染に弱く、感染の場になりやすいためメッシュを除去しないと感染が治まらないことがあります。当院では術中・術後の抗菌薬投与、術後はフィルムのシートで創部を覆って細菌が創部に入りこまないようにして感染を予防しています。 手術は腰椎麻酔(下半身麻酔)で行い、約1時間で終了します。
[腹腔鏡下ヘルニア修復術] 当院では腹腔鏡を用いて、腹腔内からヘルニア嚢を切除し腹壁を補強するメッシュを挿入するTAPP法を行っています。臍に12mmのポート、下腹部に2カ所5mmのポートを挿入し、腹腔内に炭酸ガスを注入しカメラを挿入してモニターに鼡径部を映し出して手術を行います。鼡径部切開法と比較して傷が小さいため痛みが少ないこと、漿液腫や血腫などのリスクは少ないことが長所です。また、左右に鼡径ヘルニアがある方は、小さい傷で両方の手術が可能です。しかし、全身麻酔を要するため呼吸器疾患や心臓に問題のある方は適応が難しい場合があります。合併症は出血、疼痛、腹腔内臓器損傷のリスクと全身麻酔に伴うものとして肺炎、血栓症があります。手術時間は1ヶ所1〜2時間です。術後2〜5日で退院が可能です。運動などは術後2週間後可能です。手術の創は体内に吸収される糸で体表にでないように縫合されますので、手術後の消毒・抜糸などは必要ありません。
|